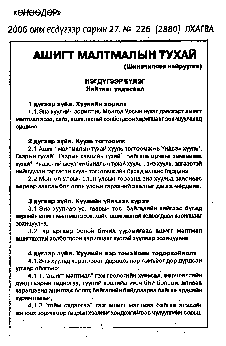「鉱山法」が改正された(2006年07月08日)
2006年春期国家大ホラル(国会)閉会の直前の2006年7月8日に、モンゴル内外の注目を集めていた「鉱山法」(1997年)が改正された。
筆者は、この改正「鉱山法」の全文をまだ入手していない。そこで、とりあえず、モンゴルの新聞によってその概要を紹介する。
鉱山法改正の要点は、以下の通り。
1)採掘権は法人にのみ付与(個人ではなく)する。
2)国内外投資家に平等に課税する(採掘権付与期間は30年、以後20年ずつ2回更新)。
3)「自動継続契約」は「投資契約」に変更する(詳細な内容は不明)。
4)地方自治体の権利を拡大する(採掘権付与決定に関する審議に参加)。
5)情報公開、経営への政府参加(持株50%まで、全額出資の外資へは34%まで)(内容はまだ不明)。
6)環境保全対策を厳格化する(500万〜1000万トグルグの罰金)。
7)採掘権料を引き上げる(5%に)。その課金の内の10〜20%を現地の自治体に、70%を国庫に納入する。
8)外国人労働者数を10%以下に制限する。(以上、ウランバートル・ポスト紙2006年07月19日付)
新聞報道から見る限り、この内容は、筆者が先に
論評したものの最大公約数を採り入れたものといえる。
ただ、モンゴル国内では、この改正「鉱山法」に批判が強い。
例えば、ガンバータル(急進的改革運動代表、鉱山法改正案作成グループに参加)は、1)環境保全対策が不十分である、という。
С.アビルメド(故О.エンフサイハンの「我がモンゴルの土地」運動に参加)は、2)政府参加条項が不十分で、1997年の鉱山法と変わらない、という。(ウランバートル・ポスト紙2006年07月19日付)
そして、このС.アビルメドは、2006年08月08日、Ж.ビャンバー、Ч.ホルツ、М.ダムディンスレン、Б.バルジンニャム、С.ボルド、Д.サンジャードルジ、Р.エルヘムバヤルたちとともに、エンフバヤル大統領に対し、「鉱山法」改正に拒否権を発動するように要請した。
その内容は次のようなものである。
3)天然資源を国家ではなく私企業によって開発しようとしている。
4)政府参加が50%以内であるということは0%もありえる(注:上記の2)と同じ)。
5)採掘権付与期間が従来の15年から30年になった。
6)採掘権付与に関する審査作業が未だ不明瞭なまま残された。
7)自然環境保全対策が不十分である(注:ガンバータルの見解と同じ)。
結局、大統領は拒否権を発動しなかった(ウヌードゥル新聞2006年08月17日付)。
一方、М.エンフボルド首相は、「ウォールストリート・ジャーナル」誌とのインタビューで、(鉱山法改正が)モンゴル鉱山部門の発展に大いに寄与するであろう、と語り、外資企業を支持することを強調した(ウヌードゥル新聞2006年08月30日付)。
これは、外資企業が当該部門への投資を回避するのを思いとどまらせようという意図がある。ただ、どう猛なハゲダカのごとき外資が今後どのような行動に出るかは未だ不明である。
「鉱山法」改正によって、外資企業への優遇措置はなくなったし、「自動継続契約」は廃止された。これらは一つの進歩であろう。
だが、モンゴルの天然資源(注:憲法によって国有であると明記されている)が外資企業によって採掘され、国外にその大半が未加工品で搬出される事態は解消されない。ガンバータルやアビルメドが指摘するように、環境保全対策も不十分である。
外資企業を排除し、国家主導で、完全な環境保全対策を実施し、天然資源を最終品にまで加工し、それを国内消費に回し、余剰品を輸出する、という形態が理想である。そのための努力が、この「鉱山法」改正を契機にして、モンゴル国民によって、主体的に行われることを筆者は望む。(2006.09.03)
(追補)筆者は、この改正された鉱山法の全文を入手できなかったが、「ウヌードゥル新聞」が2006年09月27日と29日付でその全文を掲載した。
この(新)鉱山法は、(11章)66箇条からなる。
全文を通読してみると、先に筆者が指摘したように、「一つの進歩」である、といえようか。
特に注目すべき点としてあげたいのは、第2章「鉱山部門への政府の調整」第12条「地方公共団体とその首長たちの完全な権利」であろう。
すなわち、第12条第1項で、「鉱山問題に地方自治体およびその首長たちが(それに付与された)権利を実行する。」
第12条第1項の1で、「鉱山法の条文とその施行に関し、政府決定の実行を地方自治体が行う。」
第12条第1項の2で、「その領有する土地において、特別の承認を与えられた土地を利用し、違反すれば罰金を科し操業を停止させる。」
第12条第1項の3において、「自然環境の保護、保全、住民の健康を守ること、地方公共団体予算への納入などに関し、その責務を実行し、監視する。」
これは、従来は、地方自治体の権限が不明瞭で、鉱山企業による土地奪取、目的外利用、環境汚染、牧民の土地追い立て、などに対して、有効な行動がとれなかった。そのため、
ソム(注:「町」に相当)長などによる、抗議運動(注:現代の「牧民運動」というべきもの)が展開されてきた。
彼らは、鉱山企業の不法に対処する法的権限を持たなかったからであった。
その意味で、第12条第1項の4で、「土地法に基づき、法令に明示された土地を、地方にために特別に収容する決定を出す。」、という条項が今後、有効になるだろう。(2006.10.01)