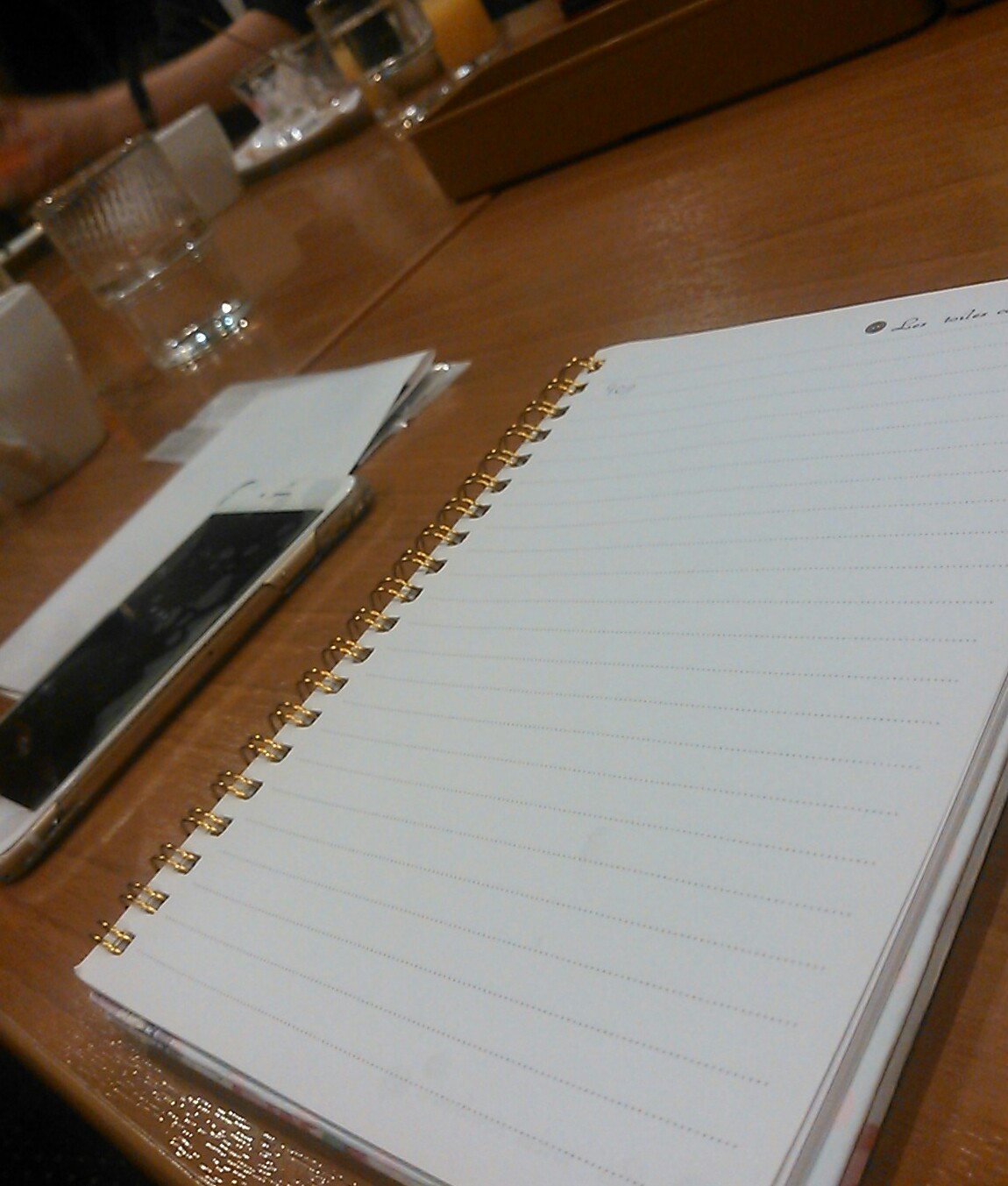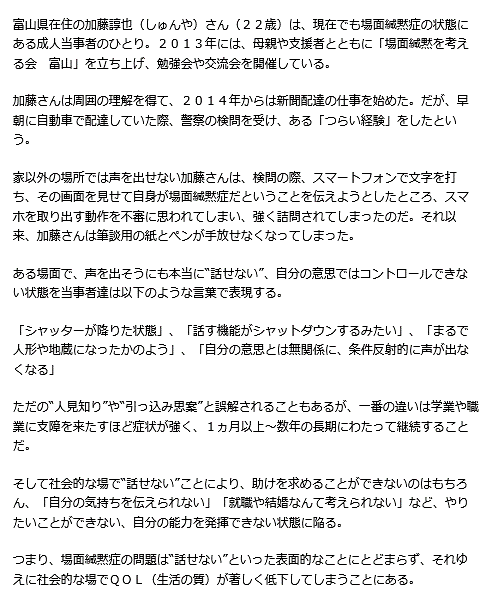会のあゆみ
〜「堀千明さんのイラスト展の鑑賞」と「けん玉教室」とのコラボ〜
日 時 : 2017年7月15日(土) 14時〜15時30分
会 場 : 富山市の「喫茶ことno葉」
内 容 : 「けん玉の正しい構え方」、「基本技の練習」、「スゴ技の披露」など
報 告 :
「けんちゃんのけん玉教室ー堀千明さんのイラスト展とのコラボー」を無事に終えることができました。 きっ茶とぎゃらりー「ことno葉」の常連客の方々や親子連れ、学校の先生方、「場面緘黙を考える会 富山」の仲間など20名近くの方々がご参加くださいました。 参加された皆さんが、けん玉の基本技である「大皿」にチャレンジされ、どんどん上手になられました。「あっ、できた!」「わあ、すごい!」などの歓声が上がり、とても賑やかで楽しい素敵な「けん玉教室」になりました。今回の企画のきっかけを作ってくださった「場面緘黙 を考える会 富山」の仲間の金子さん、堀さん、そして会場を快く提供してくださった「ことno葉」のママさんの浅岡さんへの感謝の気持ちをいつまでも忘れないようにしたいと思います。今後もいろいろな機会をいただき、経験を積み重ねていけたらと思います。
どうか、これからも温かいご支援をよろしくお願いいたします。
「場面緘黙を考える会 富山」 副代表6月に「おしゃべり会」を開催しました
日 時 : 2017年6月24日(土) 13時〜16時
会 場 : 富山市のフリースペースHOPE
参加者 : 参加者11人(HOPEの代表さん、当事者5人、保護者4人、支援者1人)でその内、初めて参加してくださった保護者の方もおられました。フリートークで、少しずつ馴染んだ雰囲気になりました。
HOPE の代表さんの存在も大きいものになりました。これからも宜しくお願い致します。
5月に「おしゃべり会」を開催しました
日 時 : 2017年5月13日(土) 19時〜
会 場 : COCO`S 黒瀬店
参加者 : 当事者やその家族、支援者など10名
内 容 : 場面緘黙に関する悩みや近況を参加者で共有しました。3月に「ランチ会」を開催しました
日 時 : 2017年3月11日(土) 12時30分〜15時
会 場 : みやの森カフェ
参加者 : 当事者やその家族、支援者など
内 容 : 場面緘黙に関する悩みや近況を参加者で共有しました。
◆◇◆第73回コラボ「秋桜月の会」 (場面緘黙を考える会富山とかんもくネットのコラボおしゃべり会)
平成28年10月15日(土)
会 場 : 富山市立八幡公民館
対 象 : 場面緘黙当事者とその保護者

《「秋桜月の会」での主な発言》
☆就労について☆
面接を心配する人が多いが、面接は質問がだいたい決まっているので、まだしゃべりやすいことが多い。
予行練習も可能。まったく知らない人の方が声は出やすいことが多い。
「シングルマザーで全緘黙」という方を見かけた。その人の場合、子どもにも上手く話すことができず、身振り手振りで伝えていた。
「何かショックな出来事があって急に声が出なくなるトラウマ性緘黙」や「ヒステリー性失声」であって、「場面緘黙」とは違う可能性があるので注意が必要。
チャレンジ雇用で自分の娘はデータを入力する仕事をしている。最初は間違いもあったが、今は慣れてきてミスもなく、仕事も速くなった。職場では周囲の理解があることがとても役立っている。
息子はけん玉が得意なので、ある福祉施設にけん玉のボランティアとして連れて行った。そのときの印象が良かったのか、施設の方から「今後は職員として来てほしい」と依頼があった。まずはボランティアとして、筆談用のメモとペンを持って働きに行くようになった。1週間、掃除やシーツ交換、草むしり等を行った。「うまくいけば就労に結びつくかもしれない」ということで支援者の方々が応援してくれた。母親として、この子の状態(場面緘黙)を伝えた。トイレに上手く行けないかもしれないので「トイレ大丈夫?」と職員の方から声をかけてほしい等と相談していたら、施設の方から「トイレも心配だったら施設利用者と同じだ」と言われた。その後、施設の方から「(別の福祉施設で働く母親と)親子で来てくれるなら、ずっと働ける」と言われたが、簡単な話ではないので断った。周囲の理解を得るのは本当に難しい。一般就労の場合、最初の段階で雇用条件など確認したり、書面で残したりする必要があったのかもしれない。
自分の息子も場面緘黙だが、今後、障害者手帳を取得するかどうかで悩んでいる。
銀行員の親類から、銀行にも障害者手帳を持って障害者枠で働いている人がいると聞いた。手帳があると選択肢が増えるかもしれないので、今後、手帳を取得するための診断書を取りに行こうかと思っている。 診断を受けて6ヶ月後でないと障害者手帳はもらえないので、よく確認したほうがいい。
☆自分の気持ちを表現する方法☆
自分の気持ちをどう表現しているのか、他の方の話を聞きたい。
自分の子どもはネットゲームが好きでスカイプを使ってチャットやメールをしている。
この前、検査のため病院に行ったら医師の前では単語が出た。心理士さんには少し喋った。知らない人には話せるのかもしれない。
小児科などの医療機関で心理士の前では緊張が下がって話せる子どもは確かにいる。
場面緘黙の中には、不安や緊張のために人前で話せないだけでなく、言語面の苦手(話を組み立てて会話するのは難しい)をもつ子どもがいる。
家庭では、本人が話したいことを大事にしてあげる。子どもが別のことに熱中しているときに親から学校の話を質問しても子どもは答えにくい。
子どもが話した内容をふくらませて会話してあげることが大事。
受け手の方が、子どもに注目して「話して欲しいオーラ」を出し過ぎると、かえって緊張が高まり話せないことはよくある。負荷をかけ過ぎないことが大事。
学校で話すのは一番難しいので最後になる。学校での発話に注目するのではなく、たとえば、「家事ができるか」「買い物ができるか」「好きなことがあるか」など、生活力をつけることが大事。そちらを充実させることがポイント。
☆生活力について☆
生活力をつけることは(緘黙と)直結しないかもしれないが、長い人生を考えたときに大事なこと。
人気アイドルグループのチケットを取るときに初めて外との接点を持った。今は一人で東京へ行けるまでになった。最初はバスの停車ボタンも押せないほどだったのに。
本人のやりたいことを突き詰めて行くのは、遠回りかもしれないが自信につながる。楽しい人生を送るための基礎になる。
好きなこと、得意なことを伸ばしたい。
母親自身が生活を楽しんで、いろんなことを話すのはいいこと。
子どもの癒しにもなるかと思って室内犬を飼った。生命力を感じる。生活に活気が出た。散歩はいいリハビリになる。散歩中に誰かが声をかけてくれるのはうれしいこと。1対1で直接話すのではなく、相手は犬を見ている。間に犬が入るとコミュニケーションしやすい。また、まだ人目が気になる場合は、夕方の散歩で帽子を被っていたりすると緊張がやわらぐ。
時間はかかってもできること、例えばお店での注文などを自分でさせる。
親がのびしろを取らない、親が先に言わないことが大事。
家事のお手伝いも始めは嫌そうにしていたが、今は慣れて自分から進んでやってくれる。
「忙しいから手伝ってくれる?」が自然な声掛け。
うちは7人家族。食器を片付けるのは娘の仕事になっている。手際がいい。これも現在の就労に活かされると感じている。
手伝えないときは、「ごめんね、お母さん」と気配りもできる。
☆反抗期について☆
不登校だったので、「学校に行け!」「嫌だ!」と親子で喧嘩になった。今はプレッシャーをかけずに様子を見ている。圧をかけないようにしている。話しかけても返事がない。朝起きるのが遅い。
行きたい気持ちがあるけど行けない、体が動かないのだと思う。
不登校の場合、子どもに登校を促していくだけでは本当の解決はない。学校に受け入れの環境が整っていればいいが、場面緘黙の理解がない学校で強いストレスにさらされることになる。
先生には親の気持ちをぶつけている。理解してくれている。自然体の方が本人も入りやすい。
スカイプで話せる相手が見つかった。最近、自分が喋れない、ということをその人に言った。
英語の方が発話しやすいという人もいる。感情がくっついてこないので言いやすい。日本語では感情がくっついてくるので恥ずかしいという思いが出るが、英語はそれがない。
イギリスなど海外では、セルフモデリングという方法がよく使われる。具体的には自分が話している場面と人(話せるようになりたい友達や先生)が話している場面の録画を編集して何度も繰り返し見る、というもの。自分がその人と喋れる感覚が醸成される。
エネルギーや力を溜めている時期もあるので、それが症状改善や行動として表面的には分かりにくい。成果が出ていないからと焦らないことが大事。
☆『状況によって声が出づらいです』提示カードについて☆
電車通学でバスを降りられなかったときにカードを出したかったが出せなかった。
先生方とロールプレイをして、本番のけん玉道二級指導員ライセンス講習会の受付で、会員証と場面緘黙の提示カードを出すことができ、受付をクリアすることができた。
いつ交通事故が起こるかわからないので、交通事故が起こった場合のロールプレイをした。
普段からカード提示に慣れていないと、緊急時にだけカードを出すことは困難。余裕がある時に出せているかどうか。慣れた環境で練習しておくことが大事。ロールプレイなどで実演練習されたとのこと、とてもいいと思った。
「場面緘黙を考える会富山〜あじさい月の会〜」
平成28年6月18日(土)
会 場 : 富山市立八幡公民館
対 象 : 場面緘黙当事者とその保護者
参加者 : 約20名(スタッフ含)
内 容 : 近況報告 意見交換

《「あじさい月の会」での主な発言》高校生の母親。幼稚園から何でもできたけど言葉がでないといわれて気になっていた。ただおとなしいだけ?と思っていた。学校では友達と一緒におるだけだった。本人は自分からは質問しない。自分から話しかけているところを私は見たことがない、という状況だった。
高校は他地区の高校に行ったら友達ができた。一緒にご飯も食べた。ラインを使って会話もできるようになった。一緒の部活に入ってもいい?など。ただ、ラインのセリフでさえ私(母)にどんな文章にしたらと相談してくる。慎重になっている。アイドルグループが好きな友達ができて二人で大阪のイベント会場へグッズを買いに行った。やっと友達らしい友達ができたと思ったが、その後、発展がない。その次のイベントのときは別の友達と行った。
最初は「〜食べとる?」「〜した?」と問いつめていた。スクールカウンセラーに相談したら「かんもくではないです」といわれた。判断基準が分からない。極度の人見知りと捉えたらいいのか悩んだ。
問い詰めることについては、スクールカウンセラーはあまりプレッシャーをかけないようにといわれ、やめた。
判断基準について(経験者の話)自分の場合は、かんもくかどうかは自分で判断した。「かんもくネット」の方とお話をしたりして自分なりに判断した。かんもくだと自分の中で受け入れるのに時間がかかった。不安な点は一人暮らしができるかどうか。大屋さんとちゃんとやり取りができるか、など。学校にいるときも学校から一歩出ると(学校の責任ではなく)自己責任だといわれる。
喋るのはずっとできなかった。親としては特別支援級がいいかなと思ったが本人は絶対嫌だといって普通級にいった。なかなか友達ができなかったがクラブに入ったら喋らないながらも何とかやっていた。
幼少期から小学校卒業まで話せなかったが、中学校で話せるようになった。高校生の時にたまたま読んだ心理学の本にかんもくが出ていて、自分はこれだと思った。今でも人に話しかけるのは苦手。かんもくだったかどうか今でも分からない。社会人になっても人としゃべるのは苦手。職場の人に悩みを打ち明けるのもできなかった。かんもくの集まりはテレビで知っていて以前から参加したいと思っていた。このような場への参加は初めてで話すのも初めて。貴重な機会だと思う。
幼稚園から小学校の終わりくらいまでかんもくの症状があった。学校では雑談はできなかったが音読はできた。家では親や兄弟と話せた。話そうと思っても言葉が出ない。次第に話さないのが当たり前になった。中学校からは少ししゃべれるようになったが片言だけ。首ふりやイエス・ノーぐらい。相手の目が見づらい。視線が怖い。高校は友達ができず、お昼も一人で弁当を食べていた。県外の大学に進学して一人暮らしをした。その後、フリーターを経て今は少人数の職場で働いている。今もコミュニケーションが上手くいかないときがある。会社に行きづらいときもある。県外にいったのは自分がかわりたいという気持ちから。「しゃべらない自分」を知らない世界に行きたかった。今の場所から逃げたいという気持ちがあったのかもしれない。
本人にはかんもくといった方がいいのか?親として葛藤している。本人を傷つけてしまうかもしれないという不安もある。
視線はいつまでも怖い。幼稚園の時からまったくしゃべれなかった。先生に「トイレに行きたい」もいえない。人前で給食を食べられない。自分から友達にしゃべりかけられない。常に人目を気にする。授業にもあまり参加できず。ただ、言葉に表さなくてもジェスチャーで意思疎通をして分かり合える友達ができたのはよかった。高校の進学を機に自分からしゃべりかけようと頑張った。就職したら声が小さいと言われたり、しゃべるのが苦手で悩んでいた時に、テレビでかんもくをやっていて自分はかんもくだと思った。かんもくと知って安心した。それまで自分を責めていた。なってよかったとまでは言えないが、他の人より敏感ですごく考えている。かんもくになって人の気持ちを考えられるようになった。チャレンジ精神が生まれにくかったが、通信で社会福祉士の資格を取りたいと頑張ってみんなに資格を取ることを伝えたら応援してくれた。寄り添ってくれて自分はすごく成長できた。自立心が芽生えた。
幼稚園からしゃべらなかったので周囲の方がおかしい、おかしいとなった。年長の時に医師から自閉症と診断された。障害が分かったら安心した。それまでは自分のせいにして気持ちが落ちていた。小学校では特別支援級に行った。接し方が少しずつ分かるようになった。かんもくとはっきり分かると親としてはどう関わればいいのかが分かるので診断にこだわるところはある。ただ、本人はどうしたってしゃべれないので辛い。
いろいろ学校を見学し、郊外の学校に行くことにした。ただ、最後は本人が決めた。本人はあの先生のところがいい、ということで決めた。一人で行けるか不安だった。その学校は携帯もダメだったので公衆電話の使い方を練習した。やっとかけられるようになった。外に出すことでいろいろ経験になった。今では一人で遠方の市へ行ったりしている。周りがサポートしてくれる。外に出してよかったと思う。
「場面緘黙を考える会富山〜如月(きさらぎ)の会〜」
平成28年2月14日(土)
会 場 : 富山市立八幡公民館教養講座学習室(和室
対 象 : 場面緘黙当事者とその保護者
参加者 : 18名(スタッフ含)
内 容 : 近況報告 意見交換

親としての心配事
学校から「しゃべらない子」と連絡があり、初めて知った。一歩でも学校から外に出ると話せるが学校の中では話せない。学校に行くのが辛くて休む日もある。今後、不登校になったらどうしようという不安がある。
感情の起伏が激しくなって戸惑う時がある・・・。
感情の起伏について
合唱団に入っており、そこでは声を出すことができる。そこで発散できている。
外で話せない分、家庭では気持ちを発散しているのかもしれない。家族とのよい関係が出来ているから安心して気持ちをぶつけてくれるのかもしれない。家庭は素直な自分の気持ちを表現できる大切な居場所ともいえる。
試練をどのように乗り越えるか?
4月から小学校6年生になる。どのように乗り越えていけるか心配。
合唱など、どんなことでもよいから、できることに注目してあげて、できたらほめるということが大切だと思う。できないことばかりに目を向けたり、誰かと比べたりするのではなく、温かい気持ちで本人を見てあげてほしい。
最高学年ということで、学校では、ただでさえプレッシャーがかかっている。「6年生なんだから!」と本人を責めて自信を喪失させないようにすることが大切。
卒業式で、名前を呼ばれたときに返事できるか、という試練があった。「返事をする代わりに手を挙げさせてほしい」と担任にお願いした。手を挙げてアピールすることはできる。先生方の中には、「手を挙げると緘黙だということが余計に目立つのでやめた方がいいのでは?」という意見もあったが、「手を挙げさせてほしい」とお願いし、実現した。
当事者の気持ち
劣等感を持ってしまう。どこに感情をぶつけたらいいか分からない。子どもの気持ちを受け止めてくれる存在が大切。
当事者は他の人よりも感受性が豊か。とても敏感。本当はしゃべりたいからよく相手を見ている。
大切なこと
無理にしゃべらせようとするのではなく、「受け入れてくれる存在がいること」「信頼できる家族がいること」が大切。
以前は緘黙という言葉も知られておらず、どこに相談していいか分からなかった。「外に連れ出さないからダメなんだ」などと言われ傷ついた。が、支援センターの方は「母親は悪くない」と言ってくださった。「一度、本人を預けてみたら?」と声もかけてくださった。思い切って子どもを預けたら少しずつ変わっていった。親だけの力では抱えきれない。周囲の支援が必要。
自分(子ども)が変われたきっかけ
電車で知らない土地へ行ってしまったが降りることも動くこともできなかった。どうしようもない危機的な状況に陥ったとき、私の場合は言葉を発することができた。それから少しずつ変わっていったと思う。
もう20歳を超えているが未だに話せない。でも最近、メールを始めたら少しずつ素直な気持ちを聞かせてくれるようになった。
オンラインゲームが好きでマイクをつけてあげたらゲーム上で知り合った相手と話せるようになった。グチも言っているようだ。まだ、学校で話せないけど家庭では話せるので、家庭で声を録音して学校で流した。クラスメイトからは「声がかっこいい」などとほめてくれた。本人もうれしかったようだ。親としては待つしかないが、いろいろやってみて「きっかけ」を与えることも大切だと感じた。
担任の先生によって本人もかわる。クラスにこのような子がいることを分かってほしい。
周囲に打ち明けることについて
周囲に緘黙のことを打ち明けるのは大変勇気のいること。
「清水の舞台から飛び降りるような気持ち」でマスコミの取材に応じて実名も出した。当初は職場の方や周囲からいろいろ言われるのではないかと不安だったが、実際には心配したほどのことはなく、むしろ温かい声を掛けてもらったり、励ましてもらったりした。
就職という壁
目下、就活中だが、緘黙でも受け入れてくれる企業がなかなか見つからないと感じている。身体障害などと比べて緘黙の場合、見た目は普通に見えるので余計に理解が得られにくい。
親としての気持ち
幼稚園の時から話せない。親としては不安であり、心配でならないが、どうにもならない。「成長とともに話せるようになるかもしれない」と思って見守るしかないというのが今の心境だ。
子どもが緘黙になると焦るけど、親としては待つしかない。いつしゃべれるようになるかは誰にも分からない。家族はSOSを発信することが大切。家族だけでは抱えきれない。勇気を出して発信すると、きょうのこの会のように多くの「つながり」が生まれる。
今後の会の持ち方について
このような場に来られる方はまだいいが、本当は来たいと思っていても来られない方もいるはず。もっと声をかけて、このような会のことを教えてあげたらいいと思う。
節目の時は親としてはいろいろ悩むもの。節目の前の時期に、また。このような場を持ったらどうだろうか。
記事のご紹介
平成28年1月30日
「秋の保護者の会」を開催しました
平成27年10月3日(土)
日 時 : 2015年10月3日(土)
14時〜17時
会 場 : 富山県民共生センター
「サンフォルテ」
参加者 : 緘黙当事者の保護者など8名
内 容 : 場面緘黙に関する悩みや近況を参加者で共有しました。
感 想
皆さんたくさんの思いを語ってくだいました。元当事者の緘黙経験の方も貴重な話をたくさんしてくださいました。つらい思いをしている人がたくさんいると感じました。また、会を開き、話し合いができたらと思います。ありがとうございました(主催者より)
「あじさい月の会」をコラボで開催!
平成27年6月6日(土)
「場面緘黙を考える会富山」と
「Knetおしゃべり会(第52回)」が
コラボで開催!
〜あじさい月の会〜
講師は、かんもくネット代表の角田圭子先生
(臨床心理士)
時 間 : 13:30〜17:00
会 場 : 富山県民共生センター
「サンフォルテ」
参加者: 18名
内 容 : 場面緘黙をめぐる情報交換
話しことばをつかわない遊び
タッピングタッチ体験
「たたいてかぶってじゃんけんホイ」の様子
タッピングタッチ体験の様子
《参加者された方々の声》
◇参加者が少ないとお聞きしていましたが、保護者や当事者、経験者など様々な方々が参加されていて驚きました。緘黙についての第一人者の角田先生の話を聞けて、本やテレビでは得られないものを知ることができました。 緘黙の子どもは、大規模校は別にして、学校に一人いるかいないかかもしれませんから、なかなか実感として多いという感じはしませんでしたが、今日の会に保護者、当事者、経験者が実際に参加されているのを見て、富山にもやっぱりいらっしゃるんだなというのが正直な感想です。そして、今日はそのような人たちの生の声を聞けただけでも、参加したかいがあったと思います。やっぱり、現在進行形の人の生の声は、強く響くなと感じました。
◇貴重な機会を本当にありがとうございました。 いろんな遊びやタッピングタッチはとても楽しくリラックスできました。 また、参加された当事者やお母さん方の切実さも伝わりました。 このような機会があれば、教員や保護者の方々にも理解が深まると思います。 学校で是非とも生かしたいです。
◇角田先生の実例を多く取り入れられた話を聞くことができ、本当に意義のある時間を過ごすことができました。そして、いつも話題に出ている角田先生にお会いすることができて、嬉しかったです。期待していた以上に、素敵な方だと感じました。場面緘黙の子どもへの接し方についても事細かに解説してくださっていて、さすがだなと思いました。 また、たくさんの方々の中に、あんなふうに堂々と参加できる当事者の方も、すごいなと感じました。これからも、続けていってほしい会だと思います。 「次回は保護者の方々だけで集まるのもよいのでは…」という意見がありましたが、名案だと思います。何よりも気持ちを分かってもらえる仲間がいることに気付くことで、保護者も少し楽になるのではないかと思います。
◇学校では、場面緘黙の子どもに対して、どのような関わり方がよいか、これまで私なりに試行錯誤してきましたが、今回、角田先生から学ばせていただいた1つ1つが大変参考になりました。さっそく、学んだことを実践してみます。 「分かち合いの時間」も、とてもよかったと思います。「いろんな遊び」や「タッピングタッチ」を通して、参加者1人1人の体と心がほぐれ、お互いの「つながり」「信頼関係」が深まったからこそ、参加者それぞれが悩みを打ち明けたり、自分の歩みを話したりできたのだと思います。
「ハートネット」で場面緘黙の特集が放送!
平成27年5月28日(木)
「NHK 福祉ポータル ハートネット」で検索すると
番組の内容が確認できます!
本会ホームページ開設
平成27年3月
テレビで場面緘黙の特集が放送!
平成27年2月18日(水)
本会メンバーがNHK富山放送局ニュース富山人
「場面かん黙を知ってください」に出演しました。
情報交換会
平成27年2月11日(水)
八幡公民館 会議室 参加者11名
1 開会の言葉
- この1年余り、スタッフの都合もあって、本会としての活動が出来ず、大変申し訳なく思っている。もう一度、原点に立ち戻って交流会などの集まりをもちたいと思っている。今日の情報交換会をそのきっかけにしたい。
2 提案−これまでの成果と今後の課題−
《これまでの成果》(H25.8.7〜8講演会&交流会の感想より)
- 講演会を通して、新しい発見があり、有意義なお話でした。
- とてもよかったです。特に自己理解のために信頼関係のある支援者から話してもらうこと、その大切さを言われたのが印象に残りました。今、私が関わっている高校生の子をイメージしながら聞くことができました。いただいた資料を学校内で回覧したいと思っています。
- 場面緘黙の方々との交流を通して、私だけでなく他の方々もいろんな課題を抱えておられることを知りました。
《今後の課題》
- 専門家を招いて講演会を開催したいが費用の問題がある。
- 会を継続していくためにはスタッフを充実する必要がある。
3 実践報告−場面緘黙に関わってきた支援者からの報告−
4 意見交換
- 場面緘黙のことを知らない人が多い。知ってもらうことが本会としての第1の目的ではないか。
- 当事者やその保護者同士がつながり合うことが大切だ。
- 本会の発足当時は周りの反応がよく、参加者も予想以上に多かったが、回を重ねるにつれて次第に減っていった。会の運営の仕方をはじめ、いろんな視点から原因を探る必要がある。
- 当事者の家族としては、同じような境遇の方の気持ちを知りたい。そのためにも、当事者の家族同士で語り合う場が欲しい。
- これまで、周りには自分と同じような場面緘黙の子どもを持つ方がいなかったし、相談相手もいなかった。そのため、親の気持ちも周囲の方々になかなか分かってもらえなかった。この会に参加して、他にも同じような人がいて正直安心した。
- 場面緘黙について具体的なアドバイスが欲しいとの思いから参加した。我が子は外へ出たがらない。どう接していいか分からない。
- 気持ちの部分を共有したい。親としては、こういう場が欲しい。
- イベントのようなものを企画するのもよいのではないか。
- 会のスタッフとしては、1人でも多くの方に「参加してよかった」と思ってもらうことができるような運営を目指し、工夫したい。
5 閉会の言葉
- 本日は皆さんのおかげで、大変充実した有意義な会となった。今回、皆さんから頂いたご意見やご提案などを大切にし、みんなで創り上げていく会にしていきたい。次回は、春ごろの開催を目指して準備を進めていきたい。
かんもくネット・「場面緘黙を考える会 富山」共催
「おしゃべり会in富山【第47回】」
平成26年11月1日(土)
富山県民共生センター「サンフォルテ」 参加者13名講師:かんもくネット代表 角田圭子先生
新聞に場面緘黙の記事が掲載!
平成26年10月30日(木)
「富山の加藤さん 富山大講義にゲスト参加 『場面緘黙』症状知って−小中学校教員学ぶ−」との見出しで、本会の活動について紹介されました。詳しくは北日本新聞のページをクリックしてください。
交流会
平成25年12月14日(土)
八幡公民館 会議室 参加者8名
ふれあい遊び&交流会
平成25年10月20日(日)
八幡公民館 会議室 参加者10名
ふれあい遊び&交流会
平成25年9月29日(日)
八幡公民館 会議室 参加者9名
交流会
平成25年9月8日(日)八幡公民館 会議室 参加者11名
新聞に場面緘黙の記事が掲載!
平成25年8月8日(木)
「『場面緘黙』の症状学ぶ かんもくネット代表・角田さん富山大学で講演会」との見出しで、本会の講演会について紹介されました。
講演会&交流会
平成25年8月7日(水)〜8日(木)
富山大学【1日目】 講演会 参加者50名
講師 角田圭子先生(かんもくネット代表)
【2日目】 交流会 参加者20名
新聞に場面緘黙の記事が掲載!
平成25年7月19日(金)
「家族とは会話 でも…学校などで話せず 『場面緘黙』知って〜富山市の短大生ら交流・啓発の会発足」との見出しで、本会の設立について紹介されました。